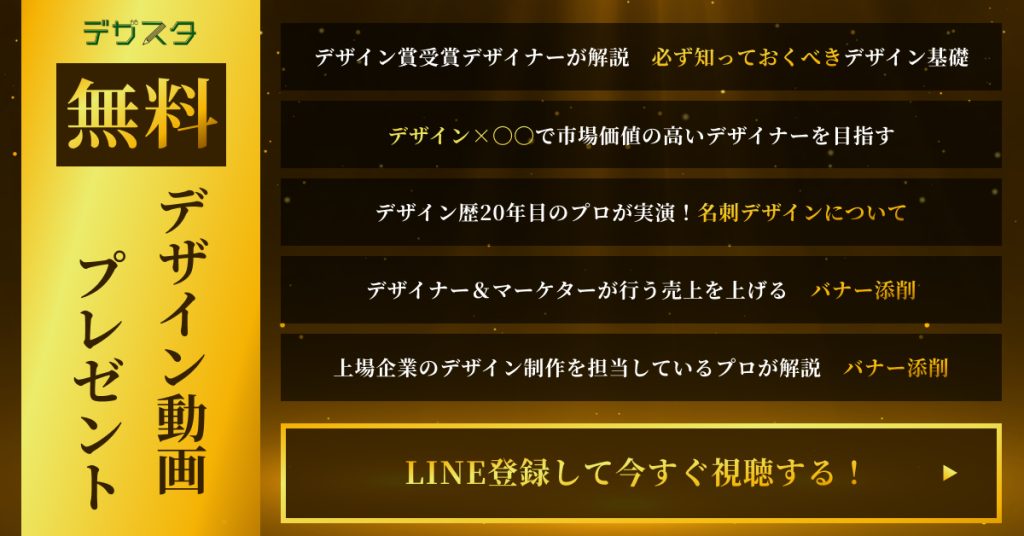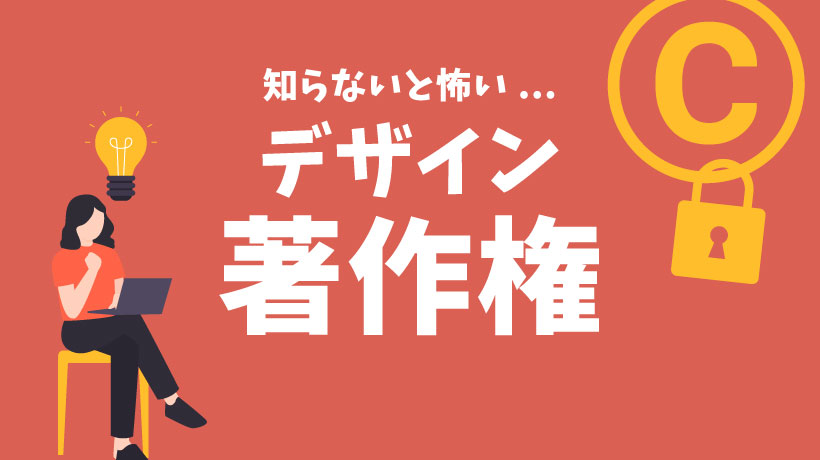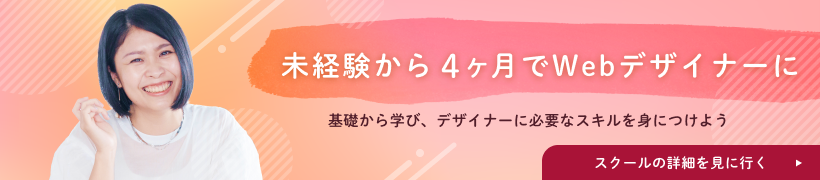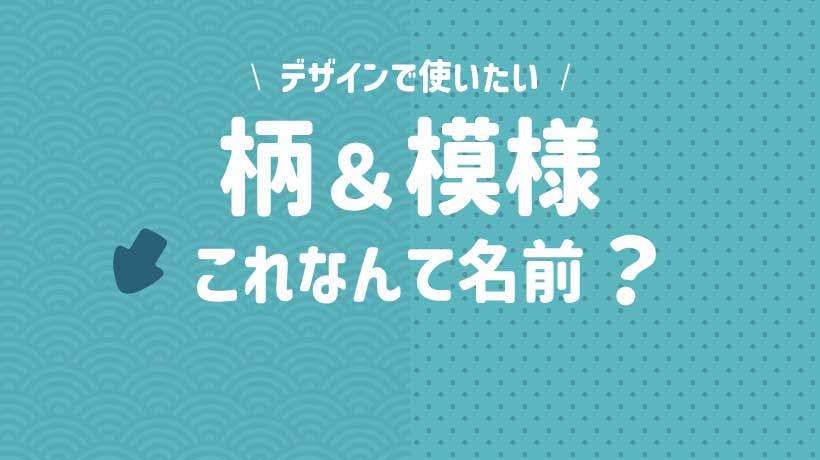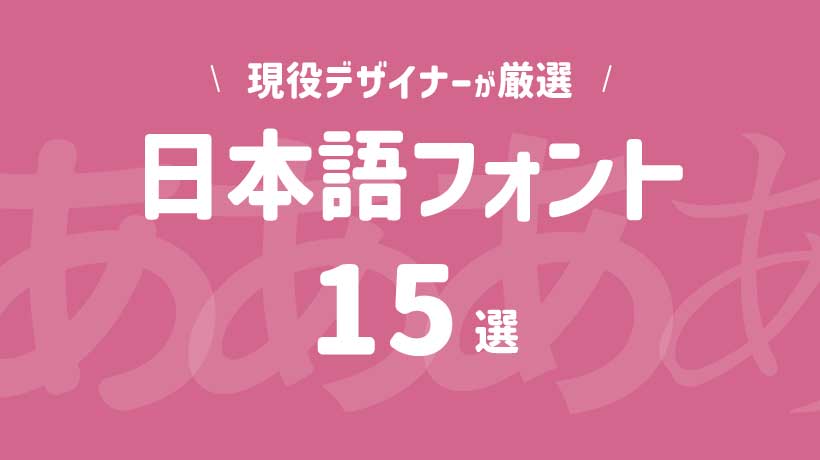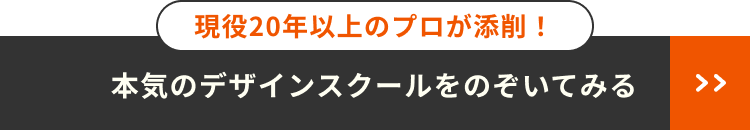- デザインの著作権って何?
- 著作権を侵害しないための注意点を知りたい
- 著作権を侵害するとどうなってしまうの?
こんな疑問や悩みを解決できる記事となっています!
デザイン制作と切り離せないのが著作権。著作権を侵害しないためには何に注意すれば良いのか、制作物の著作権は誰が持つのかなど疑問に思っている方も多いでしょう。そこでこの記事では、以下の内容について解説します!
- 著作権とは?
- トラブル回避のための重要なポイント
- 著作権にまつわる○×クイズ
- 著作権侵害をしていないか確かめる方法
デザイナーにとって著作権は避けられない問題です。この記事で著作権について理解し、注意点を意識すると、著作権に関するトラブルを未然に防げるので、クライアントともよい関係を築けるでしょう。ぜひ最後までご覧ください!
【最新イベント情報】
TOKYO Design Connect 2025開催決定!
- デザイン学習のモチベーションが保てない
- 1人で勉強していると孤独感を感じる
- デザイナーの知り合いが欲しい
デザインを勉強していると、「誰かに相談したい…」と思うことありますよね。オンラインで学ぶことが多い今だからこそ対面で会って仲間を作りませんか?勉強を一緒に頑張る、相談し助け合う、一緒に仕事をするなどイベント参加後はあなたの環境が大きく変わります。
- 初心者からデザイン歴20年のベテランまで様々な経歴を持った人と関われる!
- 現場で活躍するプロのデザイナーが行うイベント限定セミナーを受けれる!
- イベント終了後も一緒に働く仲間や新しい仕事に繋がる!

目次
著作権とは?デザインを保護する3つの権利をそれぞれの違いとともに解説

「そもそも著作権って何?」と考えている方のために、ここではデザイナーに発生する3つの権利を紹介します。
- 著作権(版権)
- 意匠権(知的財産権)
- 商標権
これらの権利をきちんと理解することで、自分がデザインしたものを守れるでしょう。ぜひ参考にしてみてくださいね!
1. 著作権
著作権とは、著作者が思想や感情を創造的に表現したものを保護するための権利です。著作物を創造した時点で発生し、行政などの手続きは必要ありません。
デザイン業界において、著作者は主にデザイナーとなり、著作権はデザイナーが制作したオリジナルの作品すべてに適用されます。著作権のある制作物に対しては、以下の行為が禁止されています。
- デザイナーの許可のない使用
- 盗用
- 販売
- 制作物の改変
著作権を侵害すると法的に裁かれる可能性があるので、注意が必要です。
著作権は、文化を発展させる重要な法律であり、デザイナーと著作物を守る大切な権利です。トラブルに発展させないためにも、しっかりと理解しておきましょう。
2. 意匠権
意匠権とは、建築物や物品や画像などのデザインを独占的に使用できる権利です。
権利を得るためには、特許庁への申請が必要です。そのため、制作した時点では権利が発生しない点に注意しましょう。
著作権と意匠権の最も大きな違いは保護される対象物です。
著作権は、文化を発展させるために作られた法律で、絵画や目で鑑賞して楽しめるものに対して発生します。一方で、意匠権は産業を発展させるために作られた法律なので、実用品やインテリアに対して発生します。
デザイナーが制作するものによっては著作権と意匠権を選別するものが難しい場合もありますが、基本的には以下のような分類を覚えておきましょう。
【著作権】
- Webサイト
- バナー
- ポスター
【意匠権】
- カバン
- ペン
- インテリア
著作権と同様に、意匠権も侵害した場合も法的に裁かれる可能性があるので、注意が必要です。
3. 商標権
商標権とは、商品やサービスに使用する商標を独占的に使用できる権利です。
デザイナーの制作物の中では主に「ロゴ」や「シンボルマーク」が対象になります。
ロゴやシンボルマークはシンプルなデザインが多いため、盗用や真似をしているなどの判断がしづらく、著作権が認められないケースがあります。そこで、ロゴやシンボルマークは商標権で権利を守ります。
商標権は著作権のように自然に発生する権利ではないため、特許庁に申請が必要です。
申請には費用がかかり、有効期限は10年です。
有効期限が切れた際には更新の必要があります。更新にも費用がかかるので注意しましょう。
ロゴやシンボルマークは多く存在しているので、制作を依頼された場合は、類似しているものがないか、必ず確認してくださいね!
【トラブル回避】著作権を持つのはデザイナー!重要なポイントを解説

著作権は制作者であるデザイナーに最初に発生します。
ただ、実際にそのデザインを使用するのはクライアントであるケースがほとんどです。その際の著作権はどうなるのか、と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。そこで、ここでは仕事をする際に意識したいことや知っておいてほしいことを解説します。
- 著作権は譲渡できる
- 契約時に著作権について明確に決める
このポイントを押さえておけば、クライアントとの著作権に関するトラブルを防ぎ、スムーズに仕事を進めることができるでしょう。ぜひ参考にしてくださいね!
1. 著作権は譲渡できる
著作権は、デザイナーと依頼者が契約を交わすことで譲渡できます。
依頼者がデザインに対して費用を支払っていても、デザイナーが著作権を譲渡しない限りそのデザインは使用できません。
著作権を譲渡するには「著作権譲渡契約書」による書面での契約が必要です。
著作権譲渡契約書には、以下の内容を記載します。
- 著作権譲渡に関する内容
- 著作権人格権(デザイナーの人格や著作物への思い入れへの配慮)
- 著作権法の条文など
著作権譲渡契約書の作成は、専門的な知識を持つ人に依頼するとよいでしょう。
2. 契約時に著作権について明確に決める
契約時には、著作権について明確に決めておきましょう。契約時に著作権の取り決めが曖昧だと、後ほど大きなトラブルにつながる可能性があります。
クライアントが制作物を使用できるのは、契約時に決められた範囲のみです。例えば、Aのサイトで使用するバナーを依頼された場合は、Aのサイトでのみ使用が認められます。Aのサイト以外で使用することは、著作権侵害に当たる可能性があります。
契約時に取り決めた使用範囲を超えて使用したり、一部デザインを変更したりする可能性がある場合、著作権の譲渡が必要です。著作権を譲渡する必要があるのか、クライアントと認識を正確に揃えて契約を進めましょう。著作権を譲渡する場合は、しない場合と比べて報酬が大きく変わるケースが多いです。
また、著作権を譲渡する場合も完全に譲渡するのか、条件付きで使用を許可するのか明確にしておくことがおすすめです。条件をつける場合は、複製のみOKなのか、デザインの色のみ変更OKなのかなど、使用条件を詳細に決めておきましょう。
【知っておきたい】著作権にまつわる○×クイズ5問

ここでは、著作権の中でも特にデザイナーが気をつけるべき点についてクイズ形式で確認していきます。
- 著作権には有効期間がある?
- 完成したデザインに一工夫すれば著作権侵害に当たらない?
- デザインの使い回しはしても良い?
- ロゴで使用するフォントは自由に使ってもよい?
- 自分でスマホで撮影した写真なら自由にチラシに使ってよい?
これらの知識はデザイン制作現場での著作権トラブルを未然に防ぐために重要です。ぜひクイズの答えを考えながら読んでみてください。
1. 著作権には有効期間がある?
答えは、○です。
著作権の保護期間は著作者の死後70年と定められています。
ちなみに、デザインを保護するための意匠権は特許庁に出願してから25年、商標権は登録日から10年と決まっています。
著作権、意匠権は有効期限の更新ができませんが、商標権は更新の手続きを行えば更新可能です。
2. 完成したデザインに一工夫すれば著作権侵害に当たらない?
答えは、×です。
著作者人格権で認められた権利の1つ「同一性保持権」によって保護されているため、著作者の意図に反して、付け加えたり、形を変えたりすることは禁止されています。
ただし、制作したものが既存のデザインにたまたま類似してしまった場合や既存のデザインを参考に全く違うものを制作した場合は、著作権侵害には当たりません。
3. デザインの使い回しはしても良い?
答えは、×です。
制作されたデザインを当初の目的以外で利用する場合は、二次利用となり追加料金が発生する可能性があります。
例えば、チラシのデザインを依頼されて制作したにもかかわらず、Webサイトに勝手にデザインを使用した場合は、二次利用とみなされます。
デザイナーはデザイン1ページ、バナー、写真、チラシなど細かいところまで価格設定を明確にし、クライアントに提示できるとよいでしょう。
一部分の買取が行えたり、価格調整の話をクライアントとすることができます。
一時的な二次利用に対しての価格もあらかじめ提示しておくことで、デザイナー自身を守ることができるので、価格表を作っておくことをおすすめします。
4. ロゴに使用するフォントは自由に使ってよい?
答えは、×です。
フォントにも著作権があります。
ロゴでフォントを使用する場合は、そのフォントが商用利用可能なものか確認するようにしましょう。
フリーフォントであっても、フォントによっては加工禁止の場合などがあるので、必ずフォントの使用許諾や利用規約に目を通すことをおすすめします。
5. 自分でスマホで撮影した写真なら自由にチラシに使ってよい?
答えは、○です。
写真の著作権は撮影した人に与えられます。
そのため、自分で撮影した写真の著作権は自分にあるので、安心してチラシに使えます。
ただし、写真に人物が写っている場合は注意が必要です。
人物を撮影した時には、被写体である人に肖像権という権利が発生します。
自分で撮影した写真であっても、被写体が写った写真をチラシで使用する場合は、被写体となる人の許可を必ず得るようにしましょう。
【不安解消】著作権侵害に当たらないか調べる方法3選と注意点

自分のデザインが著作権侵害に当たらないか心配している方もいるのではないでしょうか。そこで、制作物が著作権侵害に当たらないかを確認するための検証方法と注意点を紹介します。
- 参考をまるパクリにしない
- 他人の意見を聞いてみる
- Google画像検索で調べる
紹介した方法を実践すれば著作権トラブルのないデザイン制作ができること間違いなしです。ぜひ参考にしてみてくださいね!
1. 参考をまるパクリにしない
デザインの参考をまるパクリするのは、絶対にやめましょう。
多くのデザイナーは、制作前に参考画像や参考サイトなどを確認するのではないでしょうか。
それらを、あくまで参考にして制作することは問題ありませんが、故意的に真似したものは著作権侵害に当たります。
実際に日本でも、著作権侵害においての裁判がいくつも行われています。
Webデザインのレイアウトと配色については、創造物を表現する手段と考えられているため著作権侵害に当たりませんが、まるパクリは訴えられる可能性があるので注意が必要です。
トラブルに巻き込まれないためにも、既存するデザインは参考程度にしましょう。
2. 他人に意見を聞いてみる
完成したデザインが既存のものに少しでも似ているかもしれないと思ったら、他人に相談するようにしましょう。
著作権侵害に当たらないと自己判断した制作物をクライアントが使用して、もしそれが著作権侵害にあたった場合、大きなトラブルに発展します。
クライアントに迷惑をかけてしまうのはもちろんのこと、デザイナーとしての信頼を失ってしまいます。
著作権に関することは自分だけで判断せず、他人や直接クライアントに相談することをおすすめします。第三者の目線から、既存のデザインに酷似していないか判断してもらいましょう。
3. Google画像検索で調べる
デザインが出来上がったら、Googleの画像検索を行うとよいでしょう。
インターネット上に存在する類似している画像を簡単に見つけられます。
検索方法は以下のとおりです。
Googleのトップページを開いて、カメラのアイコンをクリックします。

調べたい画像(制作したもの)をドラックかアップロードします。

類似する画像が表示されるので、制作物と比較して確認しましょう。
まとめ
ポイント
- 著作権とは?
- トラブル回避のための重要なポイント
- 著作権にまつわる○×クイズ
- 著作権侵害をしていないか確かめる方法
今回はデザイナーにとって避けては通れない著作権について紹介しました。
著作権はデザイナーを守る権利でもあれば、知らずに侵害をしてしまうと大きなトラブルにもなる重要な権利です。
ぜひこの記事を参考に著作権を正しく理解して、クライアントとよりよい関係を築けるようなデザインの提案をしてくださいね!
【デザスタ公式LINE限定】500分超えのデザイン完全攻略コンテンツを今すぐGET!